2021年の日経平均株価について、チャート推移を振り返る。また昨年は2020年の反省を全く活かさなかったので、2022年は定期的にこのブログを見返すようにする。
(2020年で学んだこと)
- 大暴落は下落時ではなく、その後の2番底や3番底を狙っていく。
- 年間を通して訪れる2〜3回の買い場を掴む。
- 日経への寄与度を意識して銘柄選定をする。
- 自分の手法は日経の地合いから想定していくので、決算跨ぎは連動性が低下して想定外となりやすい。
- バリュー株でも下降トレンド中のものには手を出さない。
2021年までのチャート推移
次の大暴落もおそらく7~10年後くらいなので随分と先の話しとなるが、今回気付いた事は、大暴落後は約1年間の上昇トレンドとなる。つまり買いである。
合わせて昨年の気付きとして、大暴落時に買う必要はなく、暴落が落ち着いた後の2番底や3番底を狙っていくというものがある。改めて、2003年・2008年・2020年の大暴落後の2年間についてチャートを再確認しておく。
今現在(2021/12/30)だが、日経寄与度の高いファーストリテイリング・東京エレクトロン・ソフトバンクグループの3社も含めて振返ってみる。

チャートを再確認するのに、買うタイミングの検証として昨年の気付きであるボリンジャーバンド-3σへ接近したところが買い場として考える。赤色の四角で囲った部分となる。
■2003年~2008年(リーマンショック)。
・日経。

・ファーストリテイリング。

・東京エレクトロン。

・ソフトバンクグループ。

⇩
『暴落後の約1年間は上昇トレンド』『買い場はボリバン-3σ』、これについて概ね該当している。但し東京エレクトロンの2004年は日経の動きとは異なり下降トレンドに入っている為、2004年2月は買い場とは言えないので、日経との連動性が低い場合は該当しないとしておく。また補足として、最良の買い場はどれも暴落時の2003年3~4月であり、暴落後に最良の買い場が来たとは言えない。
■2008年(リーマンショック)~2020年(コロナ暴落)。
・日経。

・ファーストリテイリング。

・東京エレクトロン。

・ソフトバンクグループ。

⇩
『暴落後の約1年間は上昇トレンド』『買い場はボリバン-3σ』、これについて2009年も概ね該当している。但し、東京エレクトロンの2009年5月だけは高値掴みとなった可能性があるため、直近の支持線から上放れしている場合は該当しないとする。 また2010年5月のように-3σへ触れてもバンドウォークした場合は、直ぐに損切りして逃げるようにする。しかしSBGは日経とは連動せず上値を切り上げていったので、2010年5月は買い場として適正となった。補足として最良の買い場はどれも暴落時の2008年11月である。この期間も暴落後に最良の買い場が来たとは言えない。
■2020年(コロナ暴落)~現在。
・日経。

・ファーストリテイリング。

・東京エレクトロン。

・ソフトバンクグループ。

⇩
『暴落後の約1年間は上昇トレンド』『買い場はボリバン-3σ』、これについて2020年も概ね該当している。但し、東京エレクトロンとSBGの2020年8月は高値掴みとなった可能性があるため、やはり直近の支持線から上放れしている場合は該当しない とする。 また今回も2020年5月のように-3σへ触れてもバンドウォークした場合は、直ぐに損切りして逃げるようにする。 補足としてこの期間も最良の買い場はどれも暴落時の2020年3月である。暴落後に最良の買い場が来たとは言えない。
2022年の予想
今回チャートを振り返って気付いたが、長期トレンドが崩れるような暴落後は、その後のトレンドが落ち着くまでに一定の期間がある。以下のオレンジラインで囲ったのがその調整期間、ブルーの支持線は落ち着いた後の長期トレンドライン。
■2003年~2008年(リーマンショック)。

■2008年(リーマンショック)~2020年(コロナ暴落)。

■2020年(コロナ暴落)~現在。

2003年・2008年の各々について、調整局面を確認してみる。
■2003年~2008年(リーマンショック)。
暴落した2003年5月~2004年5月までの約1年間は上昇。
2004年5月~2005年5月までの約1年間は調整局面でレンジ相場。
2005年5月から本格的な上昇トレンド入り。
調整局面では、支持線を試す場面が2つあった(黒色の四角で囲った部分)。

・ファーストリテイリング。

・東京エレクトロン。

・ソフトバンクグループ。

■2008年(リーマンショック)~2020年(コロナ暴落)。
暴落した2009年3月~2010年5月までの約1年2ヶ月間は上昇。
2010年5月~2012年11月までの約2年6ヶ月間は調整局面でレンジ相場。
2012年11月から本格的な上昇トレンド入り。
調整局面ではさらに下値を更新(2011/3)してから、支持線を試す場面が2つあった(黒色の四角で囲った部分)。

・ファーストリテイリング。

・東京エレクトロン。

・ソフトバンクグループ。

■2020年(コロナ暴落)~現在。
2つのパターンを想定した。
【パターン1】
(2022/1/30追記、パターン2で進行中)
暴落した2020年3月~2021年5月までの約1年2ヶ月間は上昇。
2021年5月~2022年5月頃までの約1年間は調整局面でレンジ相場と想定。
2022年5月頃から本格的な上昇トレンド入りと想定。
調整局面では、支持線を試す場面が2つあると想定(黒色の四角で囲った部分)。

【パターン2】
暴落した2020年3月~2021年5月までの約1年2ヶ月間は上昇。
2021年5月~2023年5月以降までの約2年間以上は調整局面でレンジ相場と想定。
2023年中で本格的な上昇トレンド入りと想定。
調整局面では下値を模索してから(赤字の矢印)、支持線を試す場面が2つあると想定(黒色の四角で囲った部分)。

⇩2022/1/30追記
想定通りのため、買い始める。高値更新はせずに上値を下げつつのレンジ相場でイメージしているため、欲張らずに利確を繰り返していく。


NYダウとNASDAQのチャート推移
2021年までのNYダウとナスダックのチャートも振返っておく。
■2003年~2008年(リーマンショック)。
日経は2003年の下落幅が大きかったので、2005年から急上昇した。
ダウは安定した上昇トレンドを形成した。
ナスダックは2000年に大暴騰しているので、2003年以降の上昇は緩やかとなった。
・日経。

・ダウ。

・ナスダック。

■2008年(リーマンショック)~2020年(コロナ暴落)。
日経は2010年からの調整局面が長かったので、2013年より急上昇した。
ダウとナスダックも2010年から調整に入ったが、1年弱で上昇を始めて安定した。
・日経。

・ダウ。

・ナスダック。

■2020年(コロナ暴落)~現在。
日経は2021年からレンジ相場。
ダウは緩やかにはなったが上昇継続中。
ナスダックは急騰を継続している。
ダウやナスダックも調整が入ると考えるのが妥当、その際に日経の相関性はどうなるか??想定したパターン1とパターン2のどちらが近いか見極めていくようにする。またナスダックの調整が深くなるようであれば、主役の個別株は顔ぶれが変わる可能性があるのでこちらも見極めていく。
・日経。

・ダウ。

・ナスダック。

⇩2022/1/30追記
想定通り、ここからは今回の下落をサポートラインとしてイメージしておく。
・ダウ。

・ナスダック。

米国国債10年のチャート推移
1990年代から2017年まで長期の下降トレンドだった。


2017年にレジスタンスラインを抜けるが、2019年より再度下げている。

NYダウ(オレンジ色)と比較してみる。
リーマンショックの時は10年国債が先行して下落をはじめた(赤の矢印)。
その後、2011年頃より株価は上昇トレンド入りしたが10年国債は下降を継続した。

2020年のコロナ暴落でも、10年国債が先行して下落していた(赤の矢印)。

(2022/1/8時点)
米国国債10年は1.77を抜けてきた、可能性としてはこのまま上昇は続きそう。但しチャートを見る限りでは、過去のトレンドから今後の想定は出来ず、株価との相関性はよく分からない。

為替(ドル/円)のチャート推移
長期のトレンドラインはまだよく分からないが、中期は想定通り2021年から円安傾向。但し2017年からの5年間で値幅の小さい動きを続けているので、どこかで上か下へ大きく動くと思われる。


まとめ
2021年までを振り返って。
- 大暴落は下落時の底が最良の買い場だが、無理はせずその後の2番底や3番底を狙っていく。
- 大暴落後の約1年間は上昇して、その後に調整を挟んで長期上昇トレンドを形成していく。
- 2番底等の買い場はボリンジャーバンド-3σ。
- 但しグロース株で日経との相関性が低いものや支持線から上放れしていたら対象外。
- ボリバン-3σへ触れても下へバンドウォークしたら損切りする。
- 短期トレード目的であれば流動性のあるグロース株にする。
- 長期保有目的であればバリュー株にする。
- 自分の手法は日経の地合いから想定していくので、相関性が低下する決算跨ぎはしない。
2021年のよくなかったトレードを振り返って。
日経の地合いから売り買いをする現状の手法で、判断を誤っても2~3ヶ月我慢できれば損切りしなくても逃げることは出来た。また短期売買においては流動性のあるグロース株の方が本件に該当しやすく、右肩下がりのバリュー株の方がリスクは高い(但し今後主役の顔ぶれがバリューへ変わっていくのであれば逆の話しとなってくる)。
そして含み損となっても、1ヶ月前後でプラ転した時は方向性は間違ってなく、損切りしなければ大きな利益へと繋がっていた。但しバリュー株はそのまま下落する危険があるの注意が必要。
本件の振り返りで唯一逃げる場もなかったのはトビラシステムズ(2021/4/21買い)。他の実例と比べると特徴は、『右肩下がりのバリュー株』『日経の上昇起点(2020/11)でも逆相関して下げ続けていた』『2ヶ月後の反発でも戻して来なかった』の3点がある。該当した場合は損切りを覚悟する。
2022年の想定。
現在(2022/1/1時点)の日経は、大暴落後の上昇が一服して調整局面に入っているとみる。この調整がどこまで続くのかは、これから調整入りすると思われるダウやナスダックに対して日経がどこまで相関するかによると考える。ダウやナスダックの調整は1年弱を想定しておく。
日経の調整局面は短ければ2022年5月頃まで、長ければ2023年5月頃までと想定しておく。短い場合は現状の三角持ち合いで下値の支持線を試してから上放れ、長い場合は三角持ち合いの下値を掘って直近の安値を試してくるとイメージしておく。
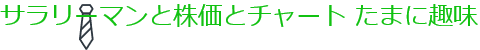
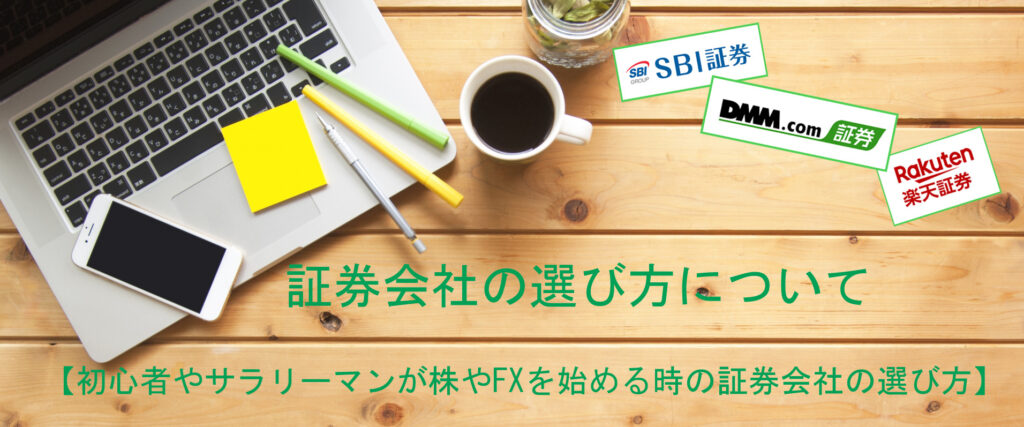
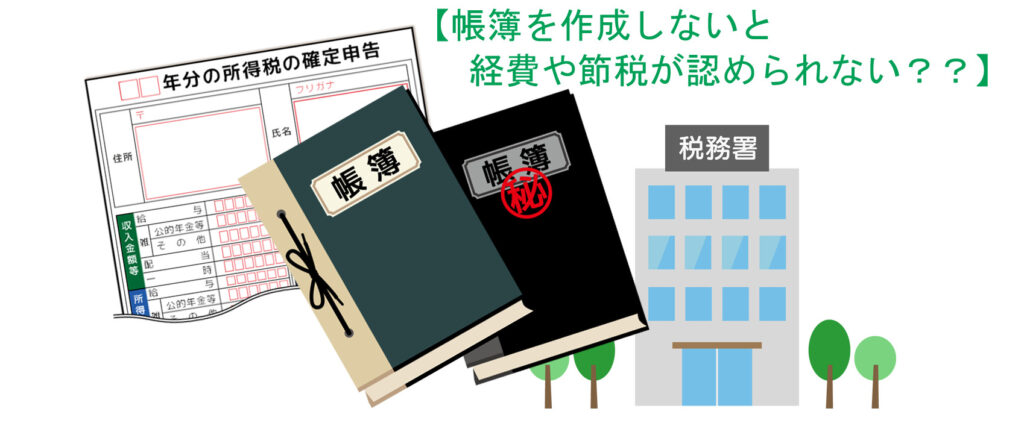
コメント